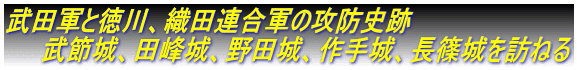 TOPPAGEへ
TOPPAGEへ2010年8月、武田軍と織田、徳川連合軍が熾烈な戦いをした三河の城を巡る
| 飯田街道 駒場の長岳寺です。ここに信玄が野田城で鉄砲で撃たれて信州に帰る途中のここ駒場で逝去し、この寺に葬られたと言い伝えらています。 | |
| 長岳寺の本殿です | |
| 長岳寺にある成就門です。説明版によると就の文字に点がありません。 門の右側に点らしきものがありました。 この門をくぐると希望が適う門であると説明書きにありました。 |
|
| 信玄を供養する13重の搭です。 | |
| 飯田街道沿いに名古屋方面に車を走らせていたらここにも信玄が葬られたとの説があります。 | |
| 立派なふるそうな石のお墓がありました。 | |
| 田峯城の大手門から入ったところに空堀跡にかかっている橋です。 いざ戦争になるっとこの橋を落として敵の侵入を阻止するように 出来ているとの説明がありました。 |
|
田峯城は1470年菅沼定信が築城。その後5代目城主定忠が武田氏に従って長篠合戦に出陣するも敗退し、徳川方に捕らえられ、田峯城は従兄弟の定利が徳川の命で城主になる。 これは表曲輪跡です。田峯城の入り口近くにあることからこのように言われている。 |
|
| 本丸跡には書院造りの御殿が復元されていました。 平成6年の竹下内閣時のふるさと創生事業の費用を使って建てたそうです。 |
|
| 当時の田峯城を守る兵士が身につけていた銅丸です。菅沼氏の紋がはいっています。 | |
| 城代家老屋敷跡から出てきた小太刀です。全体がさび付いてしまっている。 | |
| 田峯城の本丸跡にあります田峯城跡の石碑 | |
| 大手門です。復元されていました。 | |
| 物見台です。中に入ってみると上に上がる階段があります。階段はほぼ垂直に近い急勾配でした。ここから見る景色は絶景です。 | |
| 書院造りの御殿の側面からみたところです。 | |
| 物見台から下を覗くと寒狭川が見えました。敵の攻撃から守るため、木造で囲いがしてあります。 | |
| 大手門あとから本丸を望む | |
| 家老今泉道善処刑の地。 五代目城主定忠は武田方に従い長篠合戦に出陣するも大敗、留守を守る叔父定直、家老の今泉道善らは徳川方に寝返り、謀反をおこす。そのため武田勝頼とともに引き上げてきた定忠は田峯城に入れず武節城を経由して信州に敗走を余儀なくされる。復讐を誓った定忠は田峯城に夜襲をかけて謀反の一族96人を惨殺し。首謀格の今泉道善を鋸引きの刑に処した。 |
|
| 田峯観音です。三河三観音のひとつ。田峯城築城とともに城鎮護のため建立された。 | |
| 信玄が一時滞在した野だ城跡です。信玄はここで相手方の笛の名手に気をとられ鉄砲で撃たれたとも言われている。 | |
| 野田城跡に残る堀あとです。 | |
| 本丸跡に立つ野田城跡の石碑 | |
| 本丸あとに続く急な階段 |
| 武節城跡です。永正年間(1504〜1521年)、田峯城の支城として 菅沼定信が築城。1556年「武節谷の戦い」下條信氏の攻撃で落城。 1571年武田信玄が三河侵攻を始め、2万5000の兵を率いて飯田 から南下し、杣路峠を越えて城下に迫り、武節城は戦わずして軍門に 下った。1573年松平信康の初陣で、武節城を攻める。 |
|
| 武節城の空堀跡です。 | |
| 武節城の本丸跡 | |
| 本丸跡 | |
| 二の丸跡 |
| 足助城入り口にある冠木門が復元されています。 足助城は西三河山間部を治めた土豪、鈴木氏の根城。 松平清康(徳川家康の祖父)に攻められ服属したが、 清康の死とともに離反する。1554年、一時今川方につくが、 1564年の松平元康(後の徳川家康)来攻より松平の家臣となる。 後、武田軍三河来襲の際この足助城も武田側の手に落ちるが、 信玄の死と共に松平信康が奪回。旧主鈴木氏を城代とした。 1590年、高天神城での戦い等で武勲をあげたとして鈴木氏は 1万石を与えられ、家康の江戸転封と共に関東へ移り、足助城は廃城となる。 |
|
| 南の丸遠景です。土手の小さな石垣は当時のもの | |
| 南の丸曲輪です。 | |
| 南の丸曲輪です。 | |
| 西の丸曲輪です。 | |
| 西物見台です。 | |
| 炊事をした小屋 | |
| 本丸の高櫓と長屋です。 | |
| 城主の部屋です。 | |
| 足助城の歴史を詳しく説明してくれた受付のおじさん。お世話になりました。 シルバー人材センターから派遣された人? |
| 作手城(亀山)城 応永年間(1394〜1428年)頃、築かれた奥平貞俊の城。その後、貞久−貞昌−貞勝−貞能−貞昌〔信昌〕と続く。1573年奥平貞能、貞昌は、古宮城の武田軍に攻撃を受けるが、石堂ヶ根・田原坂などに転戦し、武田軍は敗走した。この戦功が認められ、1575年貞昌は信長より長篠城主を命ぜられ、「長篠、設楽ヶ原の戦い」では武田軍の猛攻を受けたが、篭城に堪え、織田・徳川軍を大勝へ導いた。貞昌は信長の一字を貰い「信昌」と改名し、新城城へ移り、家康の長女亀姫を正室に迎えた。1602年信昌の四男〔松平〕忠明が1万7000石を領して亀山藩を立藩 。1610年伊勢国亀山へ6万2000石で転封となり、小川又左衛門氏綱が入るが、1619年廃城となる。現在は曲輪、空堀、土塁など多くの遺構が残る。 |
|
| 両側が草木がぼうぼうの細い道を登って少し歩くと作手城(亀山)本丸跡にでます。 | |
| ここが本丸入り口です。 | |
| 本丸跡です。 | |
| 本丸跡にたつ石碑 | |
| 本丸跡はかなり広い | |
| 西曲輪跡。 | |
| 土橋跡 | |
| 昔の古城の雰囲気が残る城跡。 | |
| 地元の人が城跡に俳句を作っています。 「武士達と祭りに残すお城かな」と書いてありました。 |
|
| 空堀跡らしきものがありました。 | |
| 土塁跡です。 | |
| お城の中にお地蔵さんが祭られていました。 | |
| 作手城を麓から望む。 |