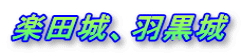 TOPPAGEへ
TOPPAGEへ
楽田城の歴史
尾張守護代織田氏の一族久長が築城したといわれている。当時は二重の堀に囲まれ、城内に櫓を築き、階上に座敷を設けた。
これが天守閣の原型だといわれている。
天正12年(1584)の小牧長久手の戦では、小牧山の徳川家康に対して羽柴秀吉の部下堀秀政が守り、のちに秀吉もこの城に入った。
合戦後、楽田城は廃城になった。
| 当寺の面影は何もない。小学校の正門前に楽田城跡の石碑が 立っている。 |
|
| 石碑を拡大したところ | |
| 大きな木が残っているのが古城らしき雰囲気を残している。 |
羽黒城の歴史
羽黒城は、建仁2年(1201)梶原景親(景時の孫)によって築城された。
景時は、頼朝に信望のあった御家人で侍所の別当として権勢を誇っていたが、頼朝が死ぬと、しばらくして幕府によって誅殺された。一部の遺族たちは、景時の孫・豊丸(のちの景親)をかこんで豊丸の乳母隅の方ゆかりの羽黒の地に逃れ、館を築き、代々住み着いた。
戦国時代になって、景親から17代目の景義は織田信長に仕えて、羽黒村3千石を領有していたが、本能寺の変で信長に殉じて討死し、梶原家は絶え、廃城となっていた。
天正12年(1584)の小牧山合戦の際、秀吉がこの城を修復させ、堀尾茂助や母方の法秀院が梶原家の出生と伝えられる山内一豊等に守らせたが、焼けてのち廃城となった。
城跡には梶原景時が建てた興禅寺がある。
| 羽黒城への登り口、以前は山全体に竹が鬱蒼としげっていたそうだが、今は竹は切り払われすっきりとしている。 | |
| 小山を登ると羽黒城址の石碑がある。 | |
| 小山の頂上から下を見ると空堀らしきものが見える。規模は相当大きなもの。 | |
| 羽黒城の全体。 | |
| 羽黒城の小山を下りると梶原景時が建てたといわれる興禅寺がある。 | |
| 立派な本堂。奈良の唐招提寺に似た外観。屋根に立派な「しび」がある。 | |
| 本堂入り口には金色の菊の御紋がきらきらと輝いていた。 | |
| 大きな岩。説明版によると慶応年間入鹿池が決壊したときに流れた石。重さ15トン。 | |
| お寺の裏に羽黒城時代の土塁の一部が残されていた。 |
前に戻る TOPPAGEへ